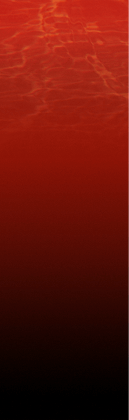赤い海
世界には赤い海がある。以前TVでその海の特集をしていた。
TVで見る映像は冗談ではなくホントに赤い色をしていて、
驚愕した記憶がある。
右の図は合成して作ったが、コレくらい赤い海だった。
赤い海と聞くと赤潮を思い出すが、赤潮とは原理が違うそうで、
プランクトンは、ほぼいない海なのだそうだ。
そもそも海が青くみえるのは太陽光の成分の青系統以外を
海が吸収してしまうからだそうだ。
ちなみに、この海の特殊性はコレだけでない。
海底はとても暗く、水深5mほどの位置でも図のように真っ暗になってしまう。
また、住んでいる魚は水深が浅いにもかかわらず、深海系の魚が多い。
水温は一定で太陽光は赤い水にさえぎられているので浅いにもかかわらず、
深海と同様の環境をしている。
赤い水はしょっぱくない。海なのに真水なのである。
赤い水は川から海に流れており、源は大湿原から染み出す水である。
大湿原の植物はボタングラスが多くこれがタンニンを水に溶け込ませている。
いわば、紅茶と同じ原理で赤いのである。
赤い水は淡水で軽いので上の方に層をつくる+内海なので波が起こらずまざらない。
と特殊な条件も重なり赤い海ができたのだそうだ。
また、深海魚などの生物しかいない理由は、タンニンのせいで太陽光がさえぎられ、
植物プランクトンが育たないので、限られた食べ物のみ食べられる生き物のみ生存する
特殊な環境だからだそうだ。
一度は見てみたいものである。
ちなみにこの赤い海の名前はバサースト湾だそうだ。
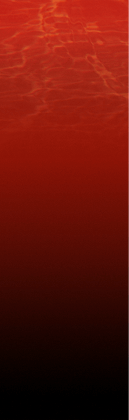

TVで見る映像は冗談ではなくホントに赤い色をしていて、
驚愕した記憶がある。
右の図は合成して作ったが、コレくらい赤い海だった。
赤い海と聞くと赤潮を思い出すが、赤潮とは原理が違うそうで、
プランクトンは、ほぼいない海なのだそうだ。
そもそも海が青くみえるのは太陽光の成分の青系統以外を
海が吸収してしまうからだそうだ。
ちなみに、この海の特殊性はコレだけでない。
海底はとても暗く、水深5mほどの位置でも図のように真っ暗になってしまう。
また、住んでいる魚は水深が浅いにもかかわらず、深海系の魚が多い。
水温は一定で太陽光は赤い水にさえぎられているので浅いにもかかわらず、
深海と同様の環境をしている。
赤い水はしょっぱくない。海なのに真水なのである。
赤い水は川から海に流れており、源は大湿原から染み出す水である。
大湿原の植物はボタングラスが多くこれがタンニンを水に溶け込ませている。
いわば、紅茶と同じ原理で赤いのである。
赤い水は淡水で軽いので上の方に層をつくる+内海なので波が起こらずまざらない。
と特殊な条件も重なり赤い海ができたのだそうだ。
また、深海魚などの生物しかいない理由は、タンニンのせいで太陽光がさえぎられ、
植物プランクトンが育たないので、限られた食べ物のみ食べられる生き物のみ生存する
特殊な環境だからだそうだ。
一度は見てみたいものである。
ちなみにこの赤い海の名前はバサースト湾だそうだ。